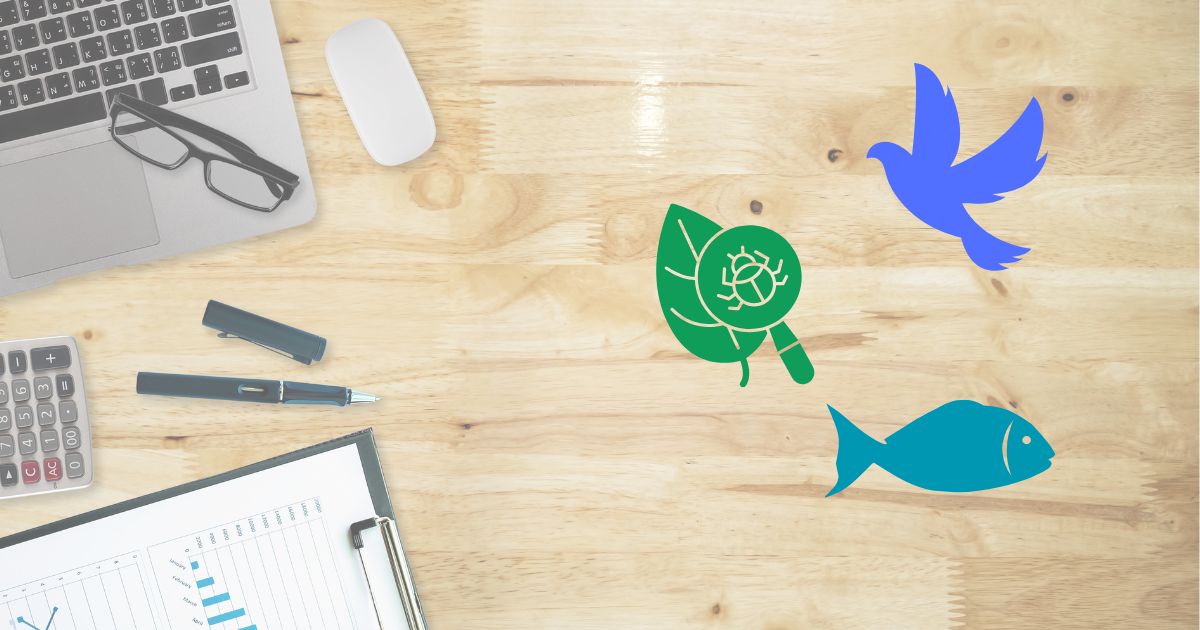広告会社で27年間やってきた仕事は、広告をつくる仕事はその一部でしかなく、企業の商品やサービスを、もっと消費者に届くように、そしてその価値を感じていただけるようにする、という仕事だったように思います。
企業がお客さまに商品やサービスを選んで頂けることは、企業活動の根幹に関わる仕事です。さらに言えば、医療やヘルスケアの領域でのお仕事が長かったこともあり、生活者(お客さま)にとっての影響や社会的な倫理観や理解の状況も考えることも重要な要素でした。
前職では、コンサルティングのお仕事の一環で研修を行う機会を頂いていたので、「マーケティング」というものを教える立場になりました。セオリーなど勉強せず、ひたすら実地でやってきた身が改めて理論を学ぶということになったのですが、ほとんどが、分かる分かる、という感覚で自分の経験が整理されていくのを感じました。
ただし、一通り整えてみても、そこにあるセオリーだけでは説明として足りないのです。それが何なのかと考えて思い出したのがこの言葉です。
「鳥の目、虫の目、魚の目」
聞かれたことがある方も多いでしょう。
当時から、自分が考えるときに使っていた脳みそはこれだと考えるとしっくりきます。
鳥の目
俯瞰するということです。鳥瞰という言葉がありますね。鳥のように上空から全体を見渡すこと。
社会の状況、取り巻く環境、業界の状況と、上空からも、少し高度を下げながらも、全体を構造的に捉えます。この構造的、といのがポイントです。構造化してみるには少し専門性や知識が必要になりますので、必要なことは学びながら全体を捉えます。
虫の目
虫の複眼で見るなどの解説がある場合もありますが、私の場合は近くにぎゅっと寄って、対象物を捉えてよくよく観察するように見るという意味合いです。虫眼鏡のイメージが近いです。対象(基本はお客さま)をよくよく観察して、その行動や思考を探る。当時は「カスタマーインサイト」を探るという言葉を多用していましたが、そのインサイト(内面性)まで掘っていくような観察を行っていきます。
魚の目
流れを見る。魚のように川や海の流れを読むこと。鳥の目や虫の目は「今」でしかないから、これからの流れを見ます。環境も、対象に対しても、これからの変化がどうなるのかを考える。変化の兆しを捉え、それが大きくなるのか、小さくなるのか、変化は速いのか、遅いのか、を考えます。
これらの3つの目を使って見て、考えることで、方針や戦略、打ち手が見えてきます。
マーケティングだけでなく、戦略策定全般に関わる話だと思いますが、自分のなかで戦略とマーケティングは混然一体となっているので、これがなくては始まらないのです。
いきなり個々の問題に目を奪われないこと、全体への視点を忘れないこと、そのうえで対象にとことん向き合うこと。例えば何か戦略や企画の提案をするとなったら、当時はこれを把握し考えることに労力の50%はかけていたように思います。そうすると、自然と戦略や打ち手は浮かび上がってくるのです。
調べてみると色々言われていて、最近はこれに蝙蝠の目(逆から見る)などもあるようですね。
とはいえ、まずは基本の3点セット、ということで意識して頂ければよいかなと思います。